工場設備の老朽化対策方法|コストを抑えて安定稼働
- inoテック
- 2025年7月31日
- 読了時間: 15分
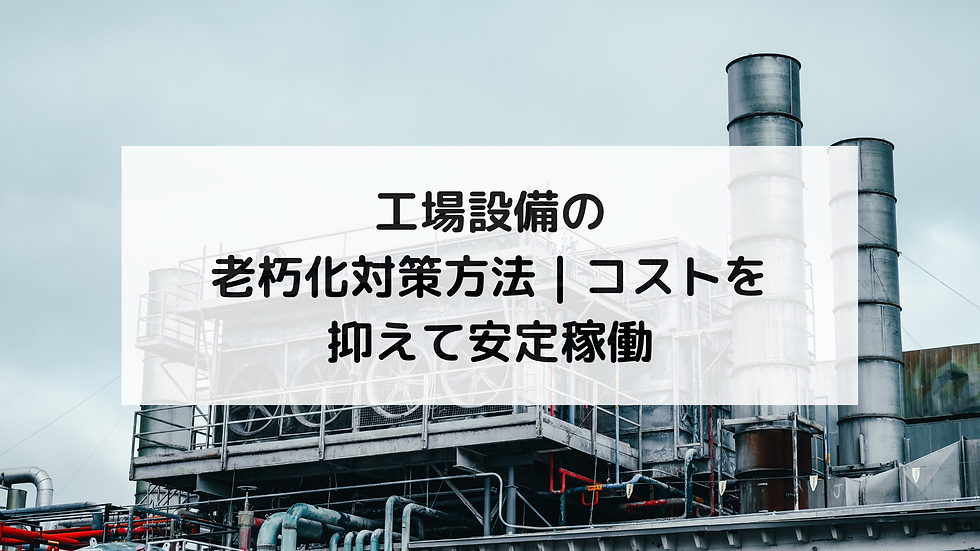
▶︎1. 工場設備の老朽化とは?その影響と見逃せないリスク

1.1 工場設備の老朽化がもたらす主なリスク
工場設備は、長年使用していると必ず劣化していきます。 「まだ動いているから大丈夫」と思って放置していませんか?
老朽化した設備を使い続けることで、現場に深刻なリスクが発生します。
特に以下のようなリスクがよく見られます。
よくある老朽化リスクとその影響
突発的な故障による生産停止
→ 突然の設備停止は、1時間あたり数十万円の損失になることも。復旧対応に追われ、納期遅延や品質低下につながります。
修理用部品の入手困難
→ 古い設備の部品がメーカーで製造終了しており、交換できないケースが増えています。代替品がないと、設備ごと更新せざるを得ません。
安全性の低下
→ 絶縁劣化やブレーカの誤作動など、安全トラブルが増加。作業者のケガや火災など、重大事故に発展するリスクも。
エネルギー効率の低下
→ モーターや制御機器の劣化により、消費電力が上昇。無駄な電気代が積み重なり、年間で数十万円規模のコスト増に。
現場での課題が複雑化する傾向も
たとえば、20年以上使っている制御盤をそのままにしていると、以下のような問題が併発しやすくなります。
回路図や仕様書が見つからない
過去にカスタマイズされていて中身が不明
修理担当者が退職していてノウハウが無い
こうした状況では、トラブル発生時の対応に時間がかかり、結果的に現場の稼働率が低下してしまいます。
こんな失敗、思い当たりませんか?
老朽化対策を後回しにしてしまう背景には、次のような思い込みがよくあります。
「動いているから大丈夫」
「予算がないから今は無理」
「いつも通りメンテナンスしていれば問題ない」
しかし、これらはすべてリスクの先送りにすぎません。
老朽化が進むと修理も困難になり、最終的には設備更新で多額の費用が発生することが多いです。
早めの対応が、結果的にコスト削減にもつながります。
1.2 老朽化によるトラブルの具体例とその背景
工場設備の老朽化は、現場のトラブルとして表面化したときにはすでに深刻な状態になっていることが多いです。 ここでは、実際に多くの現場で見られる典型的なトラブルを3つ紹介し、その背景にある問題を深掘りしていきます。
よくある老朽化トラブル3選
制御盤の異常発熱や絶縁不良
→ 古い配線や端子の劣化によって、制御盤が異常に発熱したり、絶縁が不十分になったりします。放置すると発煙や火災のリスクもあります。
PLCが突然ダウンし、装置が停止
→ 長年使用しているPLC(プログラマブルコントローラ)は、ある日突然通信が取れなくなることがあります。部品交換もできず、生産ライン全体が止まってしまうケースも。
HMI(タッチパネル)が反応しない
→ タッチパネルのバックライト切れや液晶故障により、操作不能になるトラブル。操作できないことで誤操作や生産の遅延が発生します。
トラブルの背景にある共通点
こうしたトラブルには、いくつかの共通点があります。
更新履歴や修理記録が残っていない
→ どの部品がいつ交換されたか分からず、修理対応が後手に回りがち。
予備機や代替機の用意がない
→ 故障時にすぐ交換できる準備がされていないため、復旧に数日かかることも。
属人的な管理で情報がブラックボックス化している
→ 設備に詳しい担当者が退職してしまい、トラブル対応のノウハウが継承されていない。
こうした背景があると、「設備が止まった瞬間、誰も対処できない」という状況に陥ります。特に中小製造業では、少人数で運営しているため、こうした事態が生産全体に大きな影響を及ぼします。
忙しい現場で対策が後回しになりやすい理由
現場では日々の生産を回すことが最優先になり、「とりあえず動いているから」という理由で老朽化対策が後回しにされがちです。 しかし、トラブルが起きてからでは対応が遅く、修理も高額になりやすいという落とし穴があります。
だからこそ、トラブルを未然に防ぐ仕組みづくりが欠かせません。
▶︎2. 工場設備の老朽化が進む原因とは?

2.1 一般的な老朽化の進行パターン
工場設備は、時間の経過とともに確実に劣化していきます。 とはいえ、すべての設備が同じスピードで老朽化するわけではありません。
老朽化には「進行しやすい順序」や「見落とされがちなタイミング」があるんです。
ここでは、一般的な老朽化の進行パターンと、その原因を解説します。
老朽化が進行しやすい部位や要因
電気系統から劣化が始まる
→ 制御盤や配線、スイッチ、センサーなどの電気部品は、熱や振動の影響を受けやすく、10〜15年ほどでトラブルが出やすいと言われています。
可動部品は摩耗により早期に傷む
→ モーター、ベアリング、アクチュエータなどは、連続稼働による摩耗が激しく、グリス切れや軸ブレなどの初期異常が見られることも。
塗装や配管などの外観部分は後回しにされがち
→ サビや腐食が進行していても「動いているから」と見逃されやすく、長期的に見ると漏電や事故の原因になることもあります。
こんなパターンで老朽化が進行しがちです
最初に制御盤やPLCの不具合が発生
続いて可動部品が動きにくくなる・異音が出る
最後に操作パネルや外装が不具合を起こす
このように、内側(制御)から外側(構造)へ向かって徐々に老朽化が進行するのが一般的な傾向です。
なぜ老朽化の兆候を見逃してしまうのか?
よくある理由は以下の3つです。
目に見えない変化が多いため
→ 計測器や診断ツールがなければ、異常に気づきにくい部分が多いです。
トラブルが発生するまで劣化に気づかない
→ 音や熱、電圧の変化など微細な兆候が見過ごされがちです。
日常点検が形式的になっている
→ チェックシートを埋めるだけで、実際には中身を見ていないケースもあります。
老朽化はゆっくり、しかし確実に進行します。 だからこそ、「今は動いているから安心」という思い込みが最も危険なんです。
2.2 点検不足や更新遅れによる失敗例
工場設備の老朽化は、「気づいていたのに、何も手を打たなかった」という理由で大きなトラブルに発展することが少なくありません。 ここでは、点検不足や更新の遅れによって起きがちな失敗例を3つご紹介します。
こんな失敗、意外と多いです
「半年点検で問題なし」→数日後に故障で稼働停止
→ 点検時に表面的な確認だけを行い、内部の電気回路や制御機器をチェックしていなかったため、予兆を見逃してしまったケースです。
古い制御盤を使用し続けた結果、修理不能に
→ メーカーの保守サポートが終了していたため、基板の故障に対応できず、ラインを止めて新規盤への総入替に。費用も時間も想定の3倍以上に膨れ上がったという例もあります。
予備部品を確保しておらず、緊急調達に数週間
→ 汎用機器であっても型番が古すぎて在庫がなく、メーカー取り寄せに時間がかかり、生産ラインが長期停止する結果に。
なぜ点検や更新が後回しになるのか?
現場の実情として、次のような事情があります。
生産スケジュール優先でメンテナンスの時間が取れない
点検項目が形骸化していて、意味のある確認がされていない
予算申請が通りにくく、設備更新が計画に入らない
「今、問題ないならお金をかけたくない」という考えが根強いと、いざというときに何倍ものコストが発生することになります。
点検や更新を怠るとどうなる?
点検不足や更新の遅れは、以下のような形で現れます。
トラブルの前兆(発熱・異音・応答遅れなど)に気づけない
突然の故障で復旧に数日〜数週間かかる
現場が対応できず、外部業者への緊急依頼でコストが増加
適切な予算配分ができず、更新タイミングを完全に見失う
定期的な点検・計画的な更新が“最も安くて安全な保険”になります。
▶︎3. 工場設備の老朽化に気づくサインと初期対応

3.1 故障や異音など、見逃しがちな初期症状
工場設備の老朽化は、いきなり重大な故障として現れるわけではありません。 その前には必ず「小さなサイン」が出ています。
この小さな異常に早く気づけるかどうかが、トラブルを未然に防げるかどうかの分かれ道です。
よくある初期症状とは?
モーターや機械から異音がする
→ 金属のこすれるような音、周期的なガタつき音など。これは内部摩耗や軸ブレの兆候である可能性が高いです。
タッチパネルやスイッチの反応が鈍くなる
→ 誤動作やラグが生じている場合、HMIや制御回路に不具合が生じているサインです。
制御盤内部が異常に熱い
→ 熱を持っているのにファンが回っていない、基板が焼け焦げているなど、放置すると火災のリスクもあります。
機器の起動や動作に遅延が発生
→ 通常よりも起動時間が長くなったり、動作中に一時停止したりする場合は、PLCやインバータの不調が疑われます。
なぜこれらを見逃してしまうのか?
次のような理由で、初期症状に気づきにくくなっています。
「一時的なものだろう」と見なされやすい
日々の音や動きに慣れてしまい、違和感に気づきにくい
現場に異常を報告する仕組みが整っていない
特に、慣れた作業環境では“異常に気づく感覚”が鈍りやすいものです。
小さなサインを見逃さないための工夫
こうした初期症状を見逃さないためには、日常点検の中で感覚に頼らない“見える化”が大事です。
たとえば…
温度・振動センサーの設置で異常を数値で検知
モーターの電流値や負荷率を定期的に記録
操作パネルのログを取得し、エラー傾向を分析
「なんとなくおかしい」を定量的に把握できる仕組みがあるだけで、早期発見率は格段に上がります。
3.2 点検と診断で行うべきチェックポイント
老朽化によるトラブルを未然に防ぐには、定期的な点検と診断が欠かせません。 しかし、「とりあえず見回りするだけ」では意味がありません。
本当に効果のある点検を行うには、“チェックすべきポイント”を明確にすることが大事です。
ここでは、現場で見逃されやすいが、実は重要な点検項目を具体的に紹介します。
工場設備の老朽化に対する主なチェックポイント
以下のような項目は、老朽化の早期発見に効果的です。
制御盤内部の温度・ほこり・変色
→ ファンが停止していないか、ヒートシンクに汚れが溜まっていないか確認します。 基板や端子台の変色は発熱やリーク電流のサインです。
配線やコネクタの緩み・断線
→ 揺れや温度変化によって緩んでいることが多く、接触不良による誤作動の原因になります。
制御機器(PLC、インバータ)の応答性
→ 通信エラー、起動遅延、エラーランプの点滅など。 エラーコード履歴を記録し、再発傾向があれば更新検討のサインです。
タッチパネルやセンサーの反応
→ 操作の反応が鈍くないか、動作ミスが出ていないか。センサーの劣化は誤検知・製品不良の原因になります。
モーターの振動・異音・温度上昇
→ 目視や音だけでなく、振動計や赤外線温度計を使うとより正確に診断できます。
点検の質を高める3つの工夫
写真付きの点検記録を残す
→ 曖昧な記述を避け、後の比較に役立てます。
「感覚」ではなく「数値」で判断する
→ 温度・振動・消費電力など、数値管理を取り入れるだけで、異常検知の精度が大きく上がります。
過去の点検結果と定期的に比較する
→ 小さな変化も見逃さず、劣化傾向を把握しやすくなります。
点検と診断の落とし穴に注意
注意すべき失敗例もあります。
点検が“やったことにする”だけの形式化
担当者によって点検のばらつきが出る
過去の記録が見つからず、比較できない
こうした落とし穴にハマると、せっかく点検しても効果が出ません。
点検は“気づきの起点”であり、診断は“対策の判断材料”です。 この2つが揃ってはじめて、老朽化に対する正しい行動がとれるようになります。
▶︎4. 工場設備の老朽化に有効な対策方法
4.1 設備更新だけじゃない!費用を抑えるリプレース方法
工場設備の老朽化に気づいたとき、最初に頭をよぎるのが「まるごと更新しないとダメなのか…」という不安です。 確かに、新品設備への更新は確実な方法ですが、導入コストが非常に高く、工期も長くなりがちです。
でも実は、“全部替える”必要はないことが多いんです。
リプレース(部分更新)という選択肢
老朽化した設備への対策で有効なのが、「リプレース(部分更新)」です。 これは、全体ではなく劣化が進んでいる一部の機器・構成要素だけを交換・再設計する方法です。
たとえば…
制御盤はそのままで、PLCやインバータなど電子部品だけを更新
フレームや構造体は活用し、モーターやセンサーなど可動部だけを交換
既存配線を活かしながら、新しいタッチパネル(HMI)だけ導入
このように、最小限のコストで機能を回復できるのがリプレースの魅力です。
リプレースを選ぶメリット
設備投資額を抑えられる
→ 一部機器のみ交換することで、費用はフル更新の30~50%程度に収まることも。
生産ラインを止める時間が短くて済む
→ 全面工事が不要なため、稼働を維持しながら作業が可能なケースもあります。
工場レイアウトや配線をそのまま使える
→ 工事による大規模な変更が少なく、現場の混乱も防げます。
こんな場面ではリプレースが有効です
現在の設備構成に大きな不満はないが、一部だけ不調が続いている
設備の一部がメーカー保守終了になっている
設備更新を考えているが、予算が通らない状況
ポイントは「故障してから検討する」のではなく、「そろそろ交換時期かも」と感じた段階でリプレースを検討することです。
リプレースの進め方
リプレースをスムーズに進めるためには、次の流れがおすすめです。
現状の設備の構成と動作状況を調査
劣化や不具合のある部分を特定
更新範囲・部品・工期・コストの見積もり
計画的に実施(必要に応じて夜間や休日に施工)
無理なく、ムダなく、現場を止めずに老朽化対策できるのがリプレースの最大の強みです。
4.2 制御系リニューアルの効果と導入の流れ
制御機器が老朽化すると、わずかな誤作動でも生産に影響が出ます。制御系リニューアルは、現場の安定稼働と生産性向上に直結する対策です。
主なリニューアル対象
老朽化したPLCやタッチパネル(HMI)
絶縁不良や劣化が進んだ配線・制御盤
反応遅れのあるセンサーや制御機器
導入の流れ
ヒアリング・現場調査
設計と部品選定(互換性や将来性も考慮)
試験・設置・動作確認 → 現場引き渡し
導入効果
制御ミスや不具合の削減
操作性向上・誤操作防止
トラブル予測と予防保全の実現
制御更新は「止めない工場づくり」の第一歩。トラブルが起きる前の判断がカギです。
4.3 コスト削減に直結する省エネ改善対策
老朽化した設備は、電力や空気圧の無駄が多く、見えないコストが積み重なっていることがよくあります。省エネ対策は、経費削減と設備寿命の延伸に役立ちます。
よくある省エネ改善ポイント
インバータ制御の導入でモーターの電力消費を最適化
不要時に機器を停止するオートオフ制御
LED照明・高効率モーターの導入
圧縮空気のリークチェックと対策
見える化の活用
電力や圧力の数値をリアルタイムで可視化
データに基づくムダの特定と改善
設備単位のエネルギー消費を把握しやすくなる
導入メリット
年間数十万円以上の光熱費削減につながることも
環境負荷の低減で企業イメージも向上
省エネは“設備更新なし”でも始められる効果的な老朽化対策です。
▶︎5. 工場設備の老朽化対策を成功させるポイント
5.1 外部の専門業者を活用するメリット
老朽化対策を自社だけで進めるのは難しい場面も多く、外部の専門業者を活用することでリスクを最小限に抑えることができます。
専門業者に依頼するメリット
現場調査から提案、設計、施工まで一括対応
最新技術や製品の情報に基づく適切な選定
トラブル時も迅速に原因を特定し復旧支援
よくある依頼内容
制御盤の更新や設計見直し
PLCやHMIのリプレース
メンテナンス計画の策定・実行支援
失敗しがちな自己対応例
互換性のない部品で再故障
部品選定ミスによる制御不良
工期やコストがかえって膨らむ
信頼できる業者に任せることで、失敗を回避しつつ長期的な安定運用が可能になります。
5.2 制御エンジニアリングによる総合的な改善提案
老朽化対策は「壊れたから交換」ではなく、現場全体を見渡した最適化が求められます。制御エンジニアリングの視点を取り入れることで、無駄のない改善が可能になります。
制御エンジニアができること
現場の課題をヒアリングし、根本原因を特定
設備の制御設計を見直し、生産効率を向上
部品更新だけでなく、省エネや安全性も考慮
総合提案のメリット
単なるリプレース以上の改善効果が得られる
機器同士の連携最適化によるトラブル防止
将来の拡張や自動化にも対応しやすい構成へ
よくある改善例
複数装置の制御を統合し操作性アップ
無駄な稼働時間を抑えエネルギー削減
不具合が多かった装置が安定稼働に
部分最適ではなく“全体最適”を目指すことで、老朽化対策が利益向上につながります。
5.3 メンテナンス計画で設備寿命を延ばす方法
設備の老朽化は避けられませんが、計画的なメンテナンスを実施すれば、寿命を延ばしトラブルも防げます。
計画的メンテナンスの効果
トラブルを未然に防止し、ライン停止を回避
部品の寿命管理ができ、突発交換を減らせる
設備全体の稼働率と安全性を維持できる
主なメンテナンスポイント
定期的な制御盤内の清掃・締め直し
モーターのグリスアップや振動測定
PLCやセンサーの動作確認とソフト更新
劣化部品の事前交換計画
よくある失敗例
点検の記録を残さず過去の傾向が分からない
故障してから対処する“事後保全”が常態化
点検周期や内容が担当者によってバラバラ
月単位・年単位での点検計画を立て、記録と管理をルール化することが長寿命化へのカギです。
▶︎6. まとめ:工場設備の老朽化対策で安定稼働を実現するために
老朽化は避けられませんが、正しい知識と行動でリスクを最小限に抑えることができます。 トラブル発生前に手を打つことが、コスト削減と安定稼働のポイントです。
対策の基本ステップ
日常点検で異音・発熱・遅延などの初期症状を察知
点検・診断で劣化部品やトラブル原因を特定
必要な範囲のリプレース・リニューアルを実施
制御設計を見直し、省エネ・操作性を改善
専門業者と連携し、中長期の保守計画を立案
ポイントは「壊れてから」ではなく「壊れる前に」行動すること。
生産性・安全性・コストのバランスを考えた対策で、設備はもっと長く使えます。
▶︎工場の設備改善はinoテックが徹底サポート。
PLC更新から制御盤の設計、HMI改善まで、中小製造業の現場を熟知した技術力で対応します。
まずはお気軽に、inoテックのホームページをご覧ください。

コメント